長尺動画のコンテンツ分割戦略
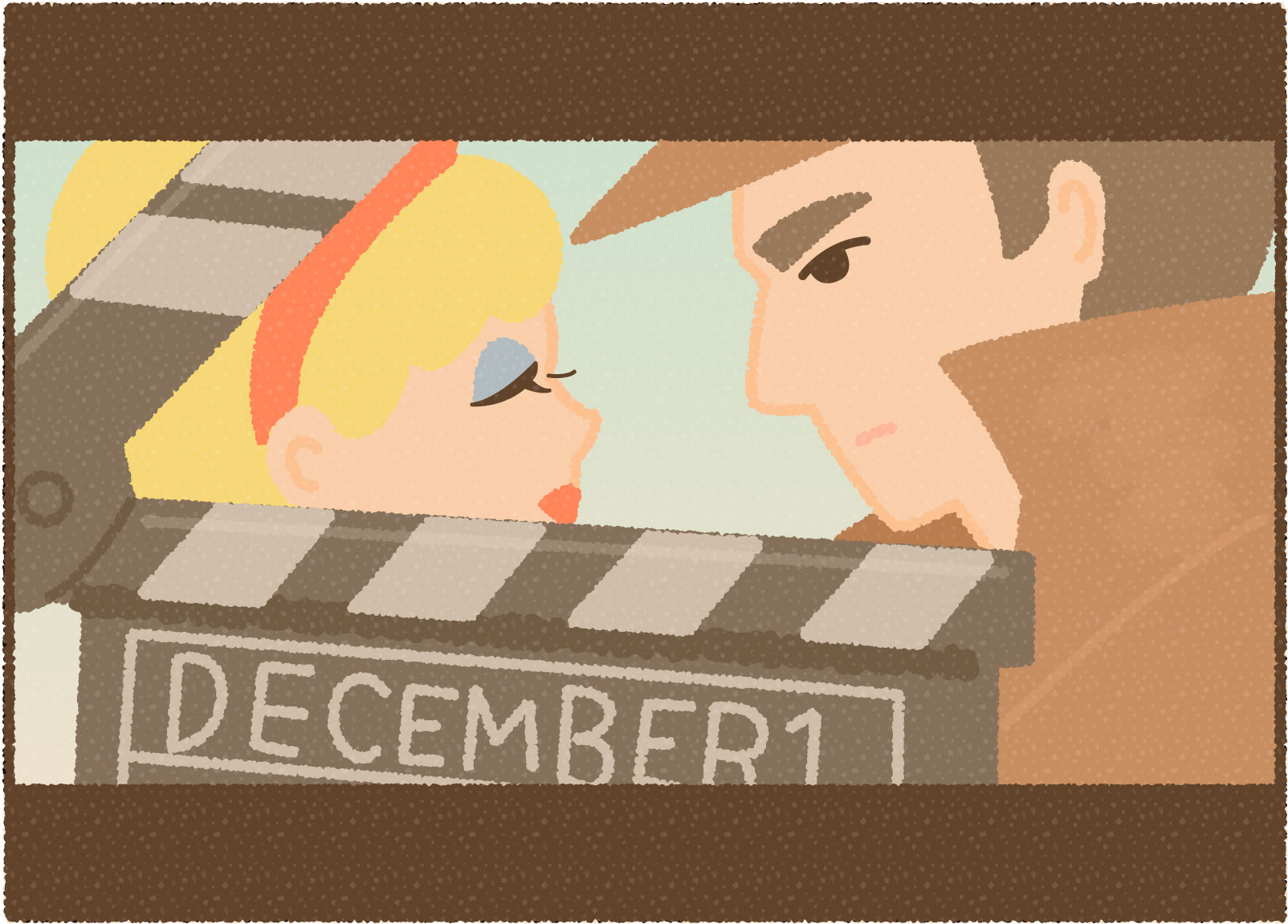
商品・サービス説明動画が長尺になってしまい、視聴してもらえないというお悩み、非常に共感できます。特に現代は情報過多で、ユーザーの集中力はごく短い時間しか続きません。長尺動画の課題を解決し、効果的に情報を伝えるための方法をいくつかご提案します。
1. 顧客が「見たい」と思えるように仕掛ける
プッシュ型とプル型の最適化

1. 「ファネル型」コンテンツ分割:興味の段階に合わせて情報を提供する
ユーザーの興味度合いに応じて、動画コンテンツを段階的に提供する考え方です。
活用場所
商品・サービスLPの詳細セクション、YouTubeチャンネル、アプリ内の詳細ページ。
入り口
超短尺の「フック動画」(5~15秒)
目的
ユーザーの注意を引き、興味を持たせる。
内容
商品(サービス)の最も魅力的・ユニークな点、あるいはユーザーの悩みを解決する瞬間を視覚的に表現します。具体的な機能説明は一切なし。印象的な映像、音楽、短いキャッチコピーで構成します。
活用場所
SNS広告、アプリ内の新着情報通知、Webサイトのファーストビュー。
中間
短尺の「ハイライト動画」/「ショートドラマ」(30秒~1分半)
目的
フック動画で掴んだ興味をさらに深める。
内容
商品(サービス)の主要な特徴やベネフィットを、**具体的な利用シーンやストーリー(ショートドラマ)**を通して魅力的に見せます。開発者の情熱や、商品が生まれる背景の一部を匂わせるのも効果的です。ユーザーが「これは自分に必要かも?」と感じるような情報に絞り込みます。
活用場所
アプリ内のトップページ、メールマガジン、SNSの投稿、商品LPの冒頭。
誘導先
「もっと詳しく知りたい」と感じたユーザー向けに、本編動画や詳細ページへのリンクを設置します。
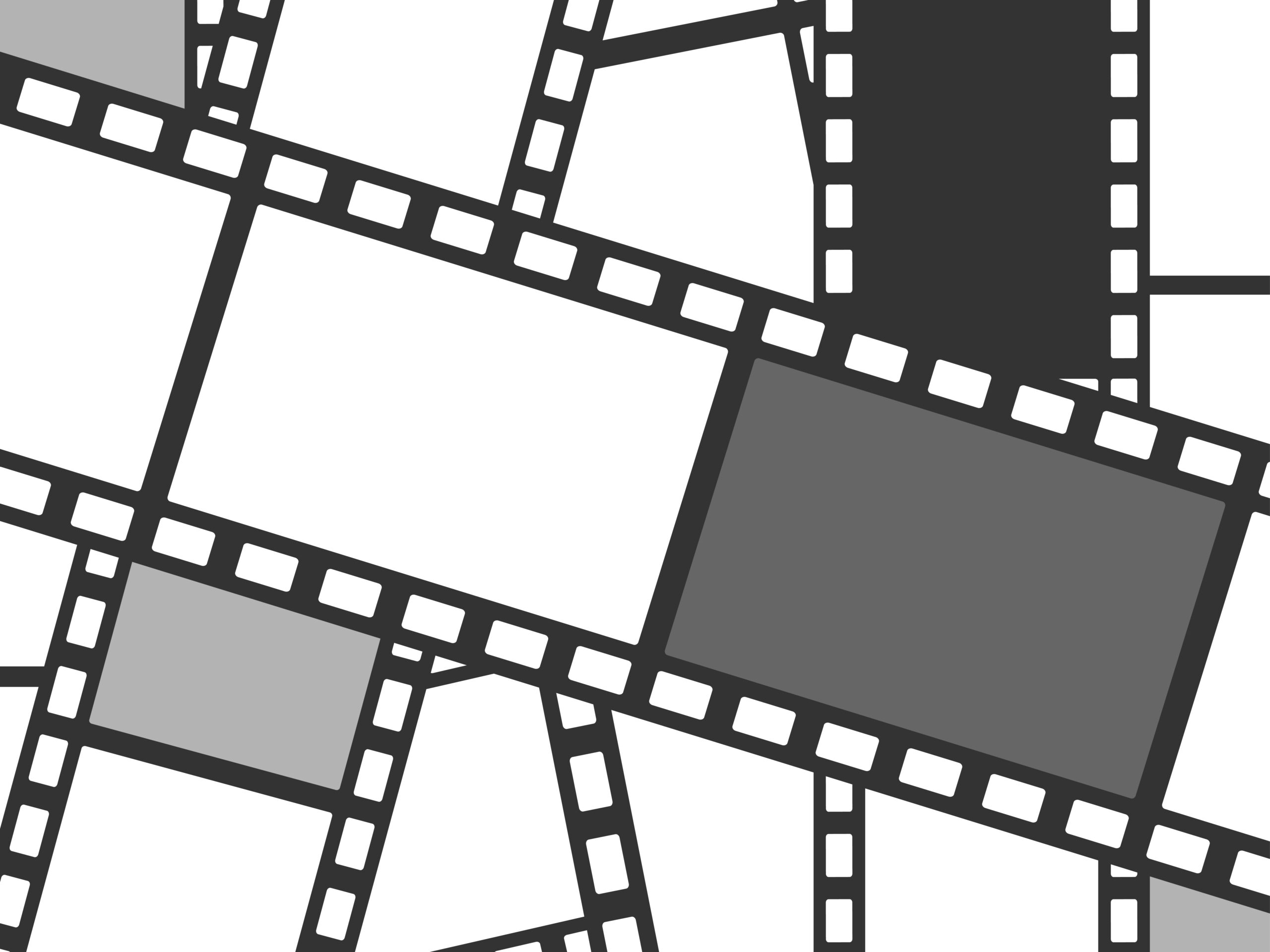
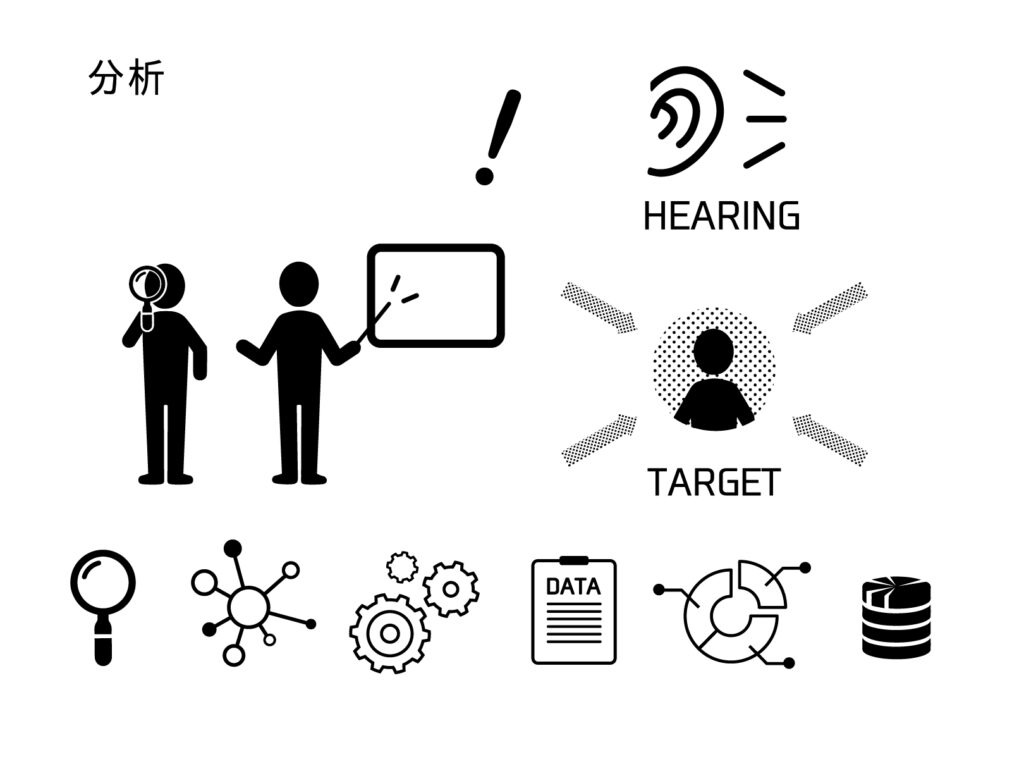
本編
中~長尺の「本編・詳細解説動画」(3分~)
目的
商品(サービス)への購入意欲を高め、疑問を解消する。
内容
商品詳細解説
各機能の具体的な使い方、技術的な優位性、競合との違いなど、購入判断に必要な情報を網羅的に説明します。
開発秘話・舞台裏
強みである「開発秘話」や「ドキュメンタリー」をここで提供します。商品(サービス)の誕生までの苦労やこだわり、品質への情熱を伝えることで、ブランドへの共感や信頼を深めます。
お客様の声・導入事例
実際に使用している顧客のリアルな声や、導入後の変化などを紹介します。
よくある質問(FAQ)への回答
購買を躊躇する要因となる疑問を動画でクリアにします。
2. 「テーマ別」コンテンツ分割:ユーザーの知りたいことに応える
一つの長尺動画を、内容ごとのテーマに分割し、ユーザーが必要な情報にすぐにアクセスできるようにします。

奥分割例
1)「〇〇(商品・サービス名)5つの特徴」
2)「〇〇(商品・サービス名)の使い方ガイド」
3)「開発者が語る〇〇(商品・サービス名)の裏側」
4)「ユーザーが語る〇〇(商品・サービス名)の魅力」
5)「〇〇(商品・サービス名名)でよくある質問」
利点
●ユーザーは自分の知りたい情報だけを効率的に見ることができます。
●YouTubeの「チャプター機能」やWebサイトの「目次」のように、各動画へのリンクを並べて表示することで、ユーザーフレンドリーになります。
●SEO対策としても有効で、特定のキーワードで検索された際に、関連する短い動画がヒットしやすくなります。
3. 「目的別」コンテンツ分割:各チャネルの特性に合わせる
商品の説明動画であっても、活用するチャネルによって最適な長さや表現方法は異なります。
1)nstagram/TikTok/YouTube Shorts向け
●短い尺(15~60秒)で、視覚的なインパクトと音楽で商品の魅力を直感的に伝えます。
●「こんなことができる」「こんな悩みを解決」といった、結論から入る構成が効果的です。
●「続きはプロフィールリンクから」など、次のアクションへ繋がる誘導を必ず入れます。
2)YouTubeチャンネル/Webサイト向け
●詳細な説明やストーリーテリングに適した尺(数分~)で、商品の機能、使い方、開発背景などを丁寧に解説します。
●シリーズ化することで、ユーザーに継続的な視聴を促します。
3)LP/アプリ内向け
●ユーザーの購買意欲が高まっている状態で表示されるため、簡潔かつ魅力的に商品のベネフィットを伝え、最終的な購入へと繋がる内容にします。
●「ハイライト動画」や「テーマ別動画」の冒頭部分を配置し、ユーザーがクリックして詳細に進めるような設計が理想的です。
実装のポイント
●明確な呼びかけ(CTA)
各分割動画の最後には、必ず「続きを見る」「詳細はこちら」「今すぐ購入」などの明確な行動を促すメッセージとリンクを設置しましょう。
●サムネイルの工夫
各動画の内容を瞬時に理解できる、魅力的なサムネイルを作成することが重要です。
●分析と改善
どの動画がよく視聴されているか、どこで離脱が多いかなどを分析し、コンテンツの改善に繋げましょう。
